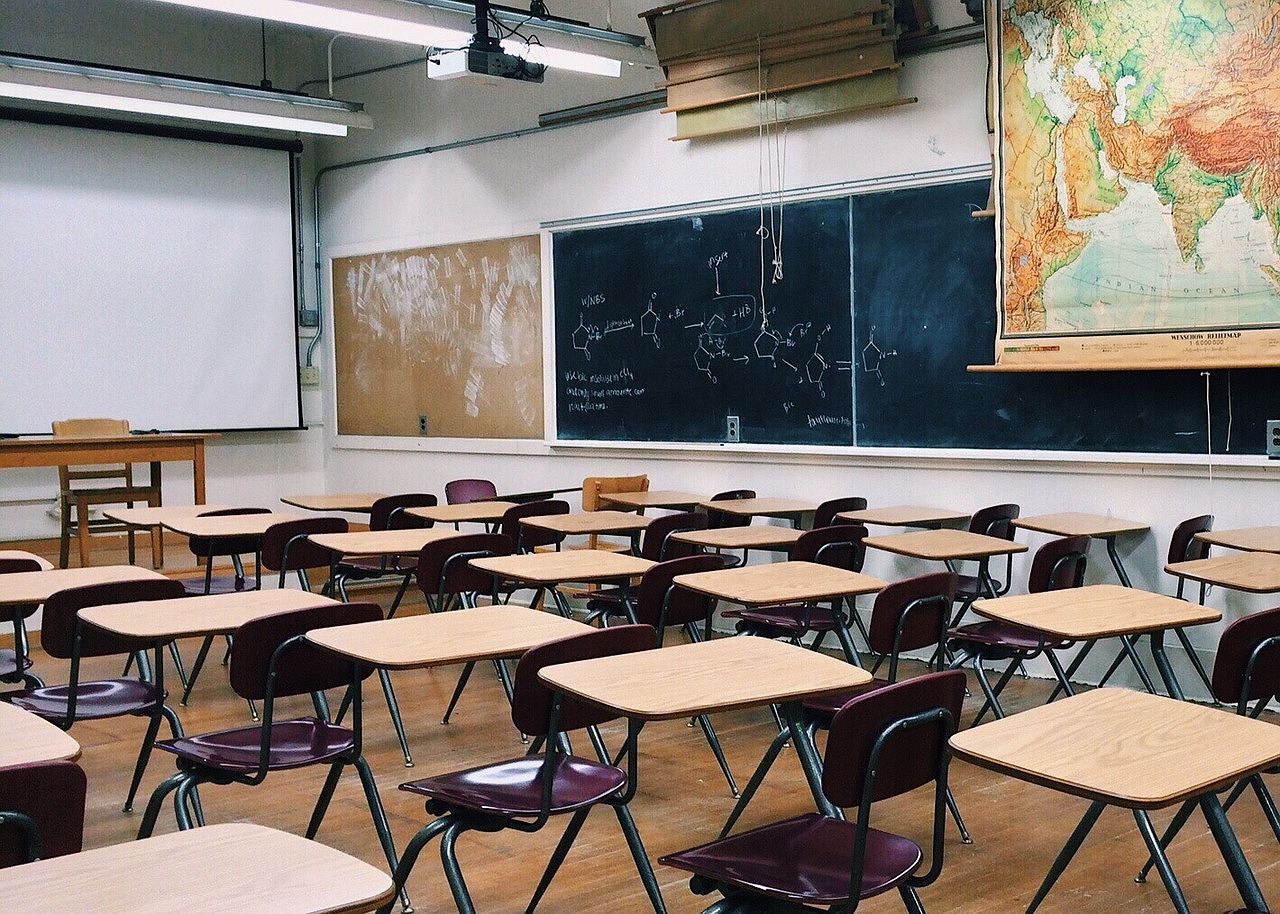不登校になりやすい家庭や子は?性格もある?
不登校になりやすい家庭や子は?性格もある?について、不登校引きこもり経験者が語ります。
不登校を経験し支援するとある程度見えてくる家庭環境や子どもの性格などがあります。
一般的に言われる、内向的な子はもちろん該当すると思いますが、実際にそれ以外の複合的な理由もあったりすると思います。
今回は、私が経験した事で感じたなりやすい傾向を解説していきます。
不登校になりやすい家庭とは?

不登校になりやすい家庭はどんな家庭があるのか?
単純に状況を考えると多い傾向は、片親や夫婦の関係が冷え込んでいる。などで、要は家族機能(関係)が上手くいってないほど不登校になりやすい子が多いと私は感じます。
実際に私が支援している人の家庭環境は、母子家庭だったり夫婦間の関係が冷え込んでいるケースが多く見られます。
また、私の家族も夫婦関係が上手くいかず、母ちゃんが私と妹を連れ家出をし、母ちゃん1人で子ども2人の面倒を私が小学生の頃から見てくれて今した。
そんな家庭環境だった私は、小学校でいじめられたり中学校で先生や部活の仲間と上手く関係が作れず悩んでいる時に、頑張っている母ちゃんの姿を見ると、内向的な性格もあって打ち明けられずにいました。
多分、当時を振り返るに私の方から堂々と母ちゃんに相談する事はできなかったと思います。
仮に相談するとしたら、普段から日常的なコミュニケーションを時間を取って交わしながら、親の方から「最近調子が悪そうやない?」といった心配する言動がない限り、私の方から相談を持ち掛ける事はなかったように思えます。
これが逆に家庭も円満で良好なコミュニケーションをとる日常があると、普段の様子や何気ない会話から私のヘルプ信号を親がキャッチし確認する事で、私も「実は最近学校で〇〇が上手くいってないんよね」と、悩みを打ち明ける事ができたかもしれません。
これは家庭環境が上手くいってないと必ず不登校になると言ってる訳ではありませんが、やはり傾向的に家庭環境の良し悪しが子どもの変化や悩みをキャッチするという意味で、良好である方が気付きやすいという意味になると考えます。
子ども自身が生活で大変なケースもある

最近ニュースなどで聞くようになった、ヤングケアラーで不登校になるケースもあるようです。
ヤングケアラーとは、本来の家族は親が子どもの面倒を見る立場にありますが、このケースはその立場が逆転し子どもが親の面倒を見たり兄弟の面倒を見るといった事が起きている現象です。
そういう日々を送っていると、子どもは家族のお世話をする事に体力と思考が持って行かれ、学校に行く体力や思考能力、時間がすり減っていきます。
そうなると、最初は遅刻から始まり最終的には休みが多くなって、そのまま学校に行かず不登校になるという事もあるようです。
しかもこのケースになると親が不安定なので、支援者が手を差し伸べようとしても、なかなか不登校の当事者や家族にアプローチする事が難しく、支援も困難を極めます。
近年、貧困や孤立が謳われていますが、その先にある一つの減少に不登校やひきこもりがあるのではないかと感じています。
こういったケースのように不登校になる理由は多岐に渡る事もあるようです。
子の性格にある?

次に不登校は子ども自身の性格にあったりするのか?
という所で言うと、傾向的に・・・
内向的で人に自分の気持ちを打ち明けたり普段のコミュニケーションを取るのが苦手
プライドが高く自分の弱みを恥ずかしいと感じ周りにも家族にも見せるのが苦手
些細な事でも色んな事を考えてしまい、結果、不安になる事が多い傾向
行動する前に考え過ぎて結果、行動をためらってしまう事が多い傾向
完璧主義で妥協できない
相手の機嫌を伺い過ぎて疲れやすい
人前に出る事を極端に嫌う
集団行動が苦手、集団の空間に居るだけでもストレスを感じやすい
などがあります。
またこれは、子どもだけでなく大人もこの傾向を持ち続けている人もいるので、そういった方達は大人であっても心が少し不安定になりやすかったりするかもしれません。
実際に私も10代20代の頃はこの傾向の要素をたくさん持っていました。
今では人前で弱みを見せる事を恥ずかしいと思う事はあまり無く、人前でも自分の考えをハッキリと伝える事ができるようになりましたが、昔はプライドが高く人に悩みや弱みを見せる事を恐れ、内向的で集団活動が苦手な人間でした。
そんな私は、根本の性格や傾向は完全に変わったとまではいかないものの、色んな成功体験や失敗体験を積み重ねる事で、自分の強み弱みが分かり、そうならない為の回避行動を覚え溜まったストレスや悩みは信頼できる人に話し聞いてもらったり、一緒に遊んで楽しい時間を過ごす事で、自分が潰れないように自分を守る行動を覚える事ができました。
ただ、私の感じた感覚ではあるものの、基本、人は誰でも自信が無かったり不安で心が押しつぶされる事が多々あったりすると思います。
でも、それを周りに見せないように立ち振る舞ったり強がったりしているように、色んな人を見てきた私は思ったりします。
つまり何が言いたいのか・・・
人はみんな大きな違いはあまり無いと言いたいのです。
人はみな不安です。
人はみな孤独です。
人はみな嫌われるのが苦手です。
でも、それは食生活と同じように栄養が取れなかったり偏った食事をするように、人の心も日常の生活で仕事もプライベートもある程度安定した生活を送らないと、心の健康が損なわれていきます。
そうなると、私のブログで取り扱っている不登校が起きてしまう訳です。
これ以外にも仕事を突然辞める。精神が崩壊する。人との関わりを拒絶する。家に篭もり出す。
という事になっていきます。
発達障がいもある?
性格というか傾向的に発達障がいの方達は、集団の中で過ごすと他児と摩擦が生じ過ぎたり、逆に集団の中で何もできずに孤立するケースもあります。
実際に過去私が支援していた小学生の発達障がいの子ども達の多くが、学校で友達と上手く関係が築けず孤立したり、集団の中に馴染めなくて不登校気味だったりという話を、保護者の方から聞いた経験があります。
発達障がいは性格による理由にはなりませんが、発達障がいの特性が実はあってまだ診断を受けていない状態で、学校で友達とトラブルが多かったり、集団に馴染めないという状況があったら、可能性として原因は性格ではなく発達障がいという可能性も否定できないと私は考えます。
なので、気になるのでしたら発達障がいの診断を受ける事を検討するのもいいかと思います。
自分の得意不得意は何なのかを知る

先ほども少し触れましたが、人はみんな得意不得意があると思います。
私の場合ですと・・・
■苦手
人が多い所や集団行動。
同じ空間でイライラしている人を感じる。
スーツを着る仕事。
表面的な人間の付き合い。
■得意
ある程度本音が言える人間の付き合い。
お互いを尊重し心が通い合える関係性。
私服(スーツを着ない)でできる仕事。
個別の対応。
年上より年下の面倒を見たり関わるのが得意。
といった、得意不得意があります。
その特徴を知った私が今している仕事が児童福祉です。
これは私の得意な所に割と当てはまっているし、支援をする上で大切な信頼関係の構築も私の得意とする分野に当てはまります。
また、基本スーツを着らず仕事ができるしお互いを尊重し合える環境も揃っています。
私の場合で紹介したように、みなさんも色んな経験を通し、成功体験や失敗体験を積み上げていきながら、自身の得意・不得意を知り、自分の特徴に合った生き方を歩んでいけたら、ある程度の人生の満足度は上がるのではないかと私は考えます。
まとめ
不登校になりやすい家庭や子は?性格もある?について、不登校引きこもり経験者が語りました。
不登校になりやすい家庭環境はできるだけ周りに頼る人やヘルプを出せる人を見つけるようにして、内向的な性格の人は自身の得意不得意を色んな経験を通して知る事で、自分に合った生き方を見つける力になると思います。
確かに傾向はあっても対策はできるので、不登校をきっかけに自身を知る良い機会に変えれると良いかなと私は思います。
もしこの記事を読んで、
・どう関わればいいのか分からない
・理由が分からない状態にモヤモヤしている
・子どもが急に話さなくなり不安だ
・一人で考えるのがつらい
と感じた方は、
個別での相談も行っています。
無理に学校へ行かせる方向にまとめる相談ではありません。
あなたやご家族の状況や気持ちを
丁寧に整理しながら、
今後の選択肢を一緒に考える相談です。
相談することで、
・気持ちが整理できる
・第三者の視点で客観的に見られる
・親子の関わり方のヒントが得られる
といったメリットがあります。
※個別相談について
社会福祉士として、市の支援機関で18年以上、
引きこもり・不登校の訪問相談支援に携わってきました。
オンラインでの家族・本人向け個別相談を行っています。
まずは 無料メール相談からでも大丈夫です。
詳しくは【個別相談のご案内】をご覧ください。
ここまで読んでくださり、
ありがとうございます。
不登校やひきこもりの状態では、
「今すぐ何かを始めなければ」
と焦る必要はありません。
ただ、もし
・学校の勉強から長く離れていて不安がある
・再登校や次の一歩に向けて、少しずつ準備したい
・家でできる学び方を知っておきたい
そう感じたタイミングが来たときのために、
自宅でできる勉強方法をまとめた記事があります。
無理に読む必要はありません。
「今の自分(子ども)に合いそうか」を考える材料として、
必要なときにだけ参考にしてもらえたらと思います。
⇒不登校やひきこもりでもできる勉強方法をまとめた記事はこちら